「すきっちゃみやざき」を運営してます、なお丸🤗です。
今回は、宮崎県宮崎市にその跡を残す佐土原城をご紹介していきます。

宮崎の戦国武将で伊藤家の本陣だね。
後に、島津の奪われるなど数々の史実がありました。
佐土原城は田島氏により築城され、伊東氏、島津氏と城主が変わった城です。
江戸時代には佐土原藩の藩庁となっていましたが、現在は山頂に本丸跡が残り
麓の二の丸跡には歴史資料館が作られています。
2004年(平成16年)には、国の指定史跡となり
また「すきっちゃみやざき」でもご紹介した飫肥城と同じく
伊藤48城の一つでもあり、続日本100名城の一つとしても認定されている城です。
ここでは、佐土原城を治めた氏族や城の歴史を紐解くとともに
佐土原城の持つ伝説などについても詳しく説明します。
佐土原城の歴史
佐土原城は14世紀中ごろ、田島休助により築城されたことから田島城と呼ばれました。
15世紀に入り伊東氏の一族の者が入場し佐土原氏を名乗るようになり
通称として佐土原城と呼ばれるようになりました。

佐土原城址の名前の由来はここからなんだ。
また、現在の佐土原町に下田島、上田島と言う地区があります。
16世紀になり1536年に田島城は焼失してしまいます。
その跡地に1542年頃に鶴松城(かくしょうじょう)という名称で再築しました。
このとき、伊東氏の居城であった都於郡城(とのこおりじょう)と同じ規模の山城として整備されました。
1625年には山の上にあった本丸を壊し、山の麓に城を移します。
城郭の老朽化による修繕費の増加への対策や1615年に幕府より発令された
武家諸法度に対する対策が理由でした。
この際に正式名称は鶴松城から松鶴城(しょうかくじょう)となりました。
明治維新後、広瀬地区に城を移築、松鶴城は取り壊されました。
しかし、明治政府の廃藩置県の政策により、広瀬の城も不要となり
新しい城が完成することなく取り壊されたのでした。
1993年には発掘調査の結果をもとに、二の丸御殿の一部を復元。
宮崎市佐土原歴史資料館『鶴松館』として公開されています。

佐土原城を治めたもの達
佐土原城は伊東氏の治めた時代、島津氏の治めた時代と大きく分けることができます。
ここでは、伊東氏の時代と島津氏の時代の歴史を紐どいていきます。
伊藤氏の時代
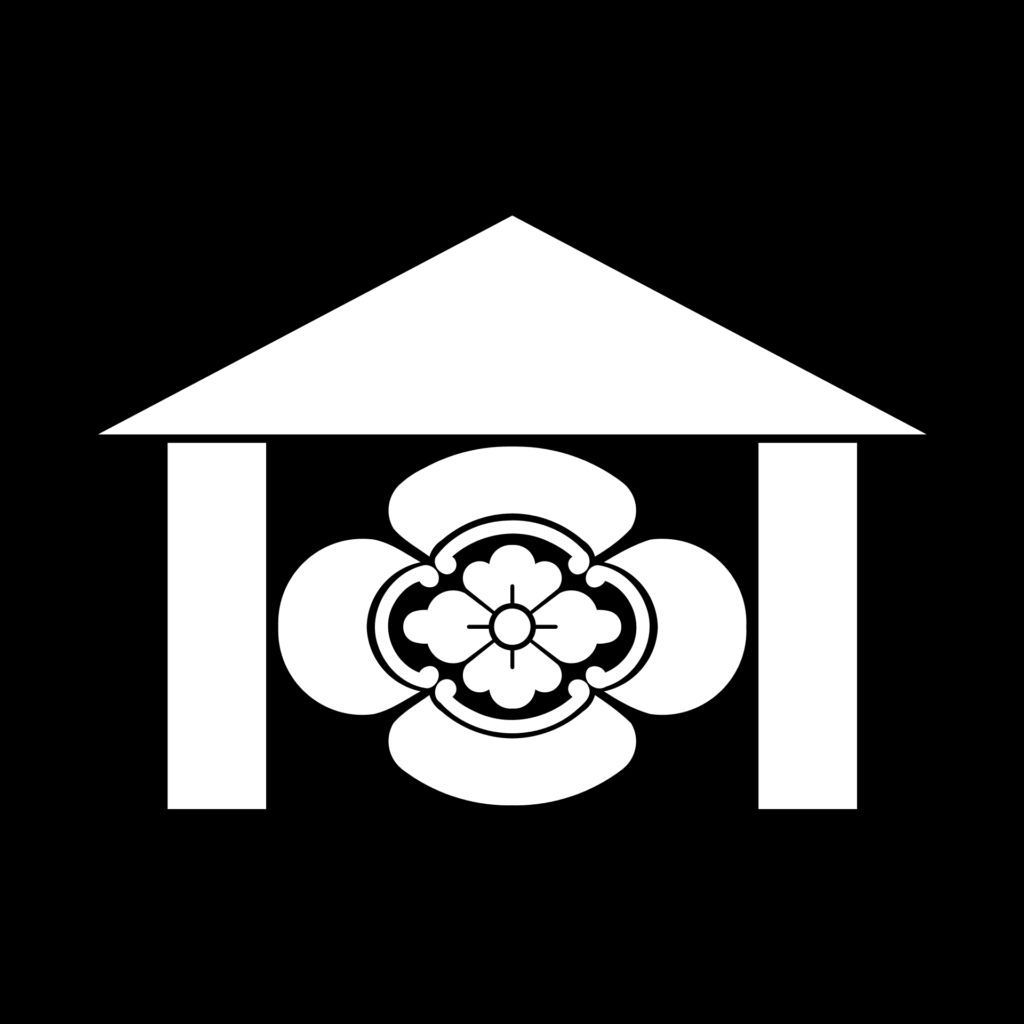
15世紀になり、伊東氏の本家筋である伊東祐賀が入場し、佐土原氏と名乗るようになり
1480年に伊東本家筋の伊東祐国が佐土原氏の養子に入り
正式に伊東氏が田島城(佐土原城)を支配するようになりました。
伊東祐国の孫で日向伊東氏9代当主であった伊東祐充が病死すると
祐充の叔父である伊東祐武が反乱を起こし、お家騒動が起こります。
鎮圧後に家督は11代当主となる伊東義祐の弟である伊東祐吉が相続しました。
ですが、わずか3年で病死し、伊東義祐が相続したのでした。
伊東義祐が当主の時代は、伊東家の最盛期でした。
義祐は飫肥を治めていた島津氏を攻め、一度飫肥を手中にしました。
その後佐土原を中心として日向国内に伊東四十八城と呼ばれる支城を築いていきました。
京文化を積極的に街中に取り入れていったことにより、佐土原城下周辺の文化は球速に発展しました。金閣寺に倣い金柏寺(きんぱくじ)を建立、念仏に励んだという話もあります。この金柏寺は現存していないものの、金柏寺釈迦堂が佐土原小学校の片隅に今も残されています。この文化発展により佐土原は「九州の小京都」と呼ばれました。
その伊東氏に衰退の陰りが見え始めるのは1572年の「木崎原の戦い」です。
現在のえびの市にあった「加久藤城」に3,000人の兵で攻め入ったのですが
島津義弘率いる300人足らずの軍勢に敗れてしまいました。
この戦いで有力な家臣が倒れ、伊東氏は窮地に陥っていくのでした。
この戦い以降、島津氏は逆襲に転じます。
次々と支城が陥落していき、1577年には飫肥城からも敗走
同年末には薩摩の島津義久の侵略により敗北し退去
その後島津義久の実弟である家久が城主として入場し
そこから島津氏が治める城となったのでした。
伊東義祐の息子の伊東祐兵は豊臣秀吉の九州討伐に参加し先導役を務めあげた功績から飫肥の地を与えられ、大名として復帰を果たします。関ケ原の戦いでは東軍に味方し宮崎城を攻撃するなど活躍したことにより、徳川秀忠より飫肥藩の所領を安堵され、飫肥藩主として廃藩置県まで飫肥の地を治めました。
島津氏の時代

島津氏は、伊東氏に勝利し日向国を手中に収め、
その後もさらに北上し九州のほとんどを制圧していきました。
時を同じくして豊臣秀吉は九州の統一に動き、九州征伐に動きました。
豊臣秀吉の進軍により島津氏は敗北します。
この九州討伐の戦では、佐土原城主であった家久が他の兄弟よりも早く単独講和を行ったものの
秀吉の陣地から城に戻ってすぐに病死。
秀吉も疑いをかけられたくないことから、すぐに義久に対し、
家久の子である豊久を佐土原城主に付けるように命じ、島津家の所領安堵を確約しました。
関ケ原の戦いの際には、豊久は一緒に参戦していた叔父の義弘を逃すために殿(しんがり)となり討死。
義弘は無事に薩摩に戻るものの、佐土原城は城主が不在となったことから徳川家預かりとなります。
しかし、島津四兄弟の従兄弟に当たる島津以久(しまづもちひさ)が3万石を与えられ
佐土原藩主として改めて佐土原城を与えられます。
その後、明治時代まで佐土原島津家が、佐土原城主として佐土原を治めたのでした。

関ヶ原の戦い以降は佐土原藩の島津。飫肥藩の伊藤に分かれたんだね。
佐土原城跡は国の史跡名勝天然記念物
佐土原城跡は2004年9月30日に国の史跡名勝天然記念物に指定されました。
史跡名勝天然記念物とは、1950年に文化財を保護するために制定された文化財保護法に基づいて
文化審議会で検討を来ない文部科学大臣が指定する史跡や名勝、天然記念物のことをいいます。
佐土原城跡はこの記念物のうち史跡区分で指定されています。
佐土原城の伝説
佐土原のお殿様には、阿蘇神社の大宮司である阿蘇氏の娘で、おキタ様という奥方がいました。阿蘇氏とは、古来から阿蘇一体を治めていた氏族でした。
このおキタ様は阿蘇さまと呼んで親しまれており、男の子も生まれ、城で楽しく過ごしていました。ところがあるとき、殿様が日向巡視の際に美少女を見初め、召し寄せ、そばに置いて可愛がるようになりました。あるとき、阿蘇さまが殿様の足を洗った後、殿様の足が腫れるということがありました。それを少女は阿蘇さまがヘビの化身だから、その毒にあてられたのだ」と言い出します。それが原因で、誰ともなく阿蘇さまのことを「蛇姫」と呼ぶようになりました。殿様もそれを信じ、阿蘇さまが生んだ男の子も、「お前もヘビの化身だろう」と柱にぶつけ殺してしまい、阿蘇さまも家来に命じて阿蘇家に送り返したのでした。
阿蘇さまは肥後の阿蘇の大池まできたとき、その池に身を投げてしまいます。水に沈んだ阿蘇さまは、ヘビの姿で現れ、「私はヘビではない。殿に捨てられた恨みからこうなった。殿や子孫にたたってやる」と言い残し、姿を消しました。
その後、殿は足を患い、生まれた姫たちも次々と不幸が続いたことから、弁天山のふもとに阿蘇さまの霊を鎮めるための阿蘇大明神を祀ったのだそうだ。

この阿蘇さまの話しは、「佐土原藩譜」(竹下勇一郎著、明治23年)に書かれており、1603年に佐土原城に入った島津以久の史実から生まれた伝説のようです。

佐土原には、更に昔になりますがもう一つの伝説もありました。
近くの史跡にも足を伸ばしてみよう
〇金柏寺釈迦堂
佐土原城祉のすぐ近くにある佐土原小学校
その東側に伊東義祐が立てたとされる金柏寺の釈迦堂が残されています。
本堂などの堂宇は、西南戦争の折、焼失してしまったのだとか。
金柏寺には、木喰上人作の丈六仏釈迦如来像が安置されていましたが
この焼失の際に下半身を失いました。上半身は助け出され、現在この釈迦堂に安置されています。
〇巨田神社
現存する社殿は室町時代に建立され今に残る巨田神社。
旧称が巨田八幡宮とされ、祭神は応神天皇、神功皇后の八幡神
上筒男神、中筒男神、底筒男神の住吉三神が祀られています。
神社の歴史は古く、創祀は831年と伝えられていますが詳細は不明。
1093年頃には周辺に宇佐八幡宮の荘園が設けられていたこともあり
宇佐八幡宮からの分霊をお祀りし巨田八幡宮と呼ばれるようになりました。
本殿は1448年に建立されており
南九州に残る中世時代の神社建築の遺構として貴重かつ重要な建物であることもあり
1978年に5月末に国の重要文化財として指定されました。
佐土原城址のアクセス
宮崎駅バス停から西都バスセンターもしくは西都原考古博物館前行きのバスに乗車、交流センター前で下車
住所:宮崎県宮崎市佐土原町上田島8227−1

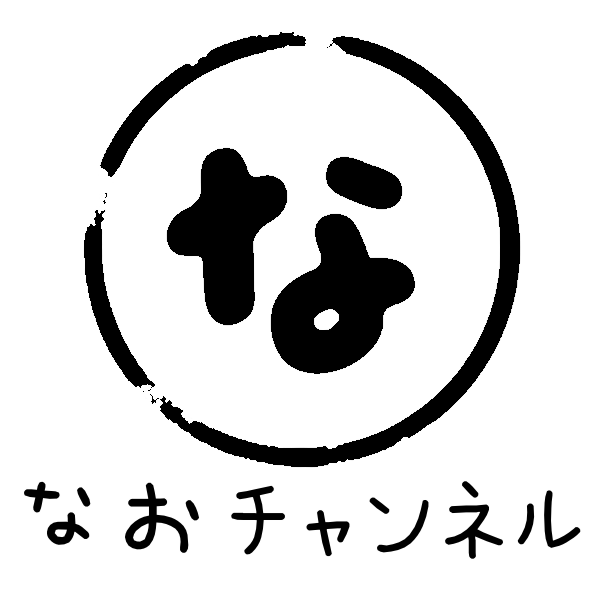 すきっちゃみやざき
すきっちゃみやざき 

誤字脱字💧
佐土原は伊東氏の分家の田島氏が長年苦労して開拓、発展させていたのに後から来た本家に乗っ取られた様で気の毒ですね。
阿蘇の姫、島津氏ではなく伊東氏にまつわる伝説では?
前島津氏、後島津氏共に阿蘇氏との婚姻の記録見当たりません。伊東氏との間に婚姻の記録ありますよ?